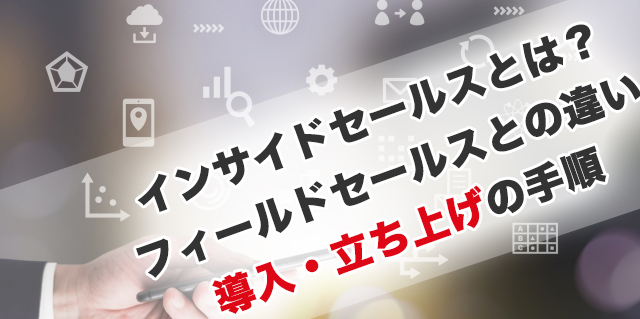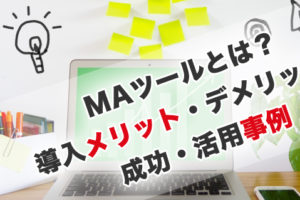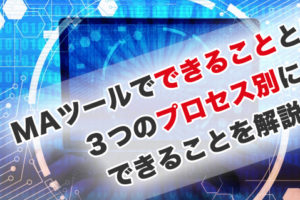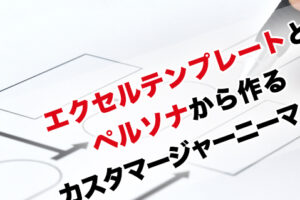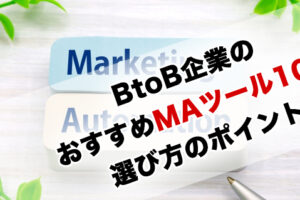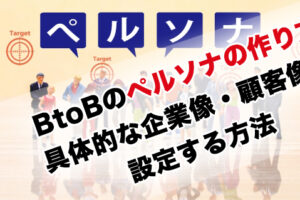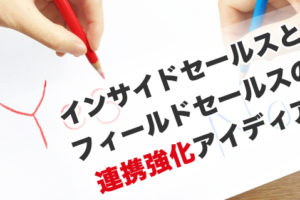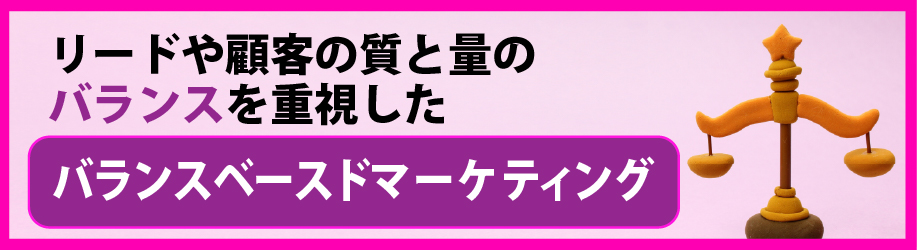インサイドセールスは、BtoBマーケティング戦略や営業戦略を効率化する上で、非常に重要な仕組みである。また、合わせてマーケティングオートメーションツールを導入することでより効率化を図ることができる。今回は、インサイドセールスとは何か、メリットやデメリット、立ち上げの手順、活用するツールなどをわかりやすく解説する。
資料一覧
インサイドセールスとは?特徴と役割
インサイドセールスとは?
インサイドセールスとは、電話やメール、DMなどを活用してリード(見込み顧客)へは訪問しない(外回りをしない)内勤型営業担当者やチーム・組織のことをいう。
インサイドセールスの特徴
インサイドセールスの特徴は非訪問・非対面での営業スタイルであることだ。このため、電話(テレアポ)、メール(メルマガやMAのシナリオメール)、オンライン会議などを活用してリードに対して営業を展開する。
非訪問・非対面であるため、多くのリードに対して効率よく接点作りを継続することができるようになる。
インサイドセールスの役割
インサイドセールスの役割としては、受注につながりにくそうなリード(確度の低い、確度のわからないリード)に対して、非対面でコミュニケーションを取りながら、関係を構築し、受注の確度を高めていくことだ。そして最終的には、営業担当者にバトンタッチする。
インサイドセールスが重要視されている背景
インサイドセールスは、主に(1)営業人材不足、(2)顧客の購買プロセスの変化といった背景から重要視されている。
いわずもがな、日本国内において今後、働き手は不足していく。このため、非訪問・非対面で多くのリードに接点が作れるインサイドセールスは、今後、営業を強化する上で非常に重要と言える。
加えて、顧客側の購買プロセスの変化も影響している。BtoBにおいて、顧客が新しい製品やサービスを購入する際、情報収集の手段としてWEBサイトやメールなどを活用しているためだ。顧客側も情報収集の効率性を考え、デジタルを活用して購入先を検討しているのである。
このため、インサイドセールスによるデジタルセールスの展開は、機会損失を防ぐためにも重要である。
インサイドセールスとフィールドセールスの違い
インサイドセールスとは外回りをしない、内勤型営業を意味する。一方、フィールドセールスとは、外回り中心の外勤型営業(訪問型対面営業)のことである。外回り中心のであるため、フィールドセールス担当者は、リードに対して電話やメールなどでアポイントを獲得し、実際に顧客先に訪問する。そして、対面による営業で受注を獲得し、その後、顧客維持なども行う。
従来の営業活動では、フィールドセールスが一般的だった。しかし、アポイントが成立し実際に訪問したところ、まだ購入の意思はなかったという例も珍しくない。こういったケースが増加すると営業工数が増大し利益を圧迫することにつながる。
インサイドセールスを導入すると、非訪問・非対面でのコミュニケーションでリードの確度の見極めが可能となり、フィールドセールスの無駄を省き、営業効率を高めることができる。
資料一覧
インサイドセールスのメリットとデメリット
インサイドセールスはメリットもデメリットもあるので、導入の前にメリットとデメリットをしっかり確認しておこう。まずはメリットを2つご紹介する。
メリット1「リードの放置が無くなり機会損失が最小化」
インサイドセールスは非訪問・非対面の営業であるため、より多くのリードに対してアプローチが可能だ。そのため、フィールドセールスが回りきれないリードに対して継続的な接点の創出が可能となる。これは営業の機会損失を最小化できるといったメリットが期待できる。
メリット2「営業の効率化」
インサイドセールスは、新規に獲得したリードに対して、非訪問・非対面で電話やメールなどを使って、リードの受注確度を確認しながらセールスする。そして、確度が高いと判断できたら、そのリードをフィールドセールスにバトンタッチする。こういった確度確認を行うことで、フィールドセールスの営業を効率化することができる。
デメリット1「人選と教育」
インサイドセールスは非対面・非訪問の営業であるが、誰でもできるというわけではない。テレアポのスキル、メール営業のスキルなど、営業スキルが必要になる。さらに、MA(マーケティングオートメーション)ツールを活用する場合は、マーケティングに関するスキルやITリテラシーも必要になる。こういった人材の人選と教育はインサイドセールスの立ち上げ当初は大きなデメリット(課題)になる。
デメリット2「長期的な営業の継続の難しさ」
インサイドセールスは、リードに対して非対面・非訪問で継続的に接点を創出しなければならない。そのため、継続的な接点づくり(例えば、継続的に電話する、継続的にメールするなど)が必要になる。これは電話やメールのネタ(何を話すか、どんなメールを送るか)の継続性を意味することになる。このネタ創出が大きなデメリット(課題)になる。いつも同じ内容で電話やメールするとマンネリ化してだんだん効果がなくなっていくからだ。
デメリット3「費用対効果の検証の難しさ」
BtoBの場合、非対面・非訪問の営業だけで受注できることは少ない。最終的には対面営業が必要になることの方が多い。そのため、インサイドセールスを立ち上げた後、費用対効果の分析で悩むことになる。インサイドセールスを立ち上げて売上は上がったのか?を分析しなければならないが、インサイドセールスだけで販売が完了するわけではないため、その分析と検証が難しいのである。
デメリット4「他部門との連携」
インサイドセールスは、フィールドセールスやマーケティング部門と連携して活動する。そのため、リード情報や案件、商談の状況を部門間で共有する必要がある。しかし、ITインフラが整っていない場合、エクセルやメールでの共有となるため、情報共有が複雑化し連携がスムーズにいかないケースがある。そのため、インサイドセールスの立ち上げには、部門間での情報共有を効率化するITインフラの導入も必要になる。
以上が、インサイドセールスのメリットとデメリットだ。なお、デメリットについては、新しい仕組みを立ち上げようとすると、必ず発生するデメリットである。そのため、立ち上げの進め方やインサイドセールスの営業戦略の設計など、立ち上げ当初の動き方が非常に重要になる。
資料一覧
テレアポ、メールなどのインサイドセールスの営業手法
では、インサイドセールスは具体的にどのような営業をするのか、代表的な営業手法をご紹介する。
テレアポ・電話営業
最も多いのがテレアポ、電話営業である。セミナーや展示会、WEBサイトでのコンバージョンなど、新規に獲得したリードに対して電話営業を行いアポイントを獲得する。テレアポの際には、確度確認も必要で、アポを取ることを目的にすると、フィールドセールスの営業効率は改善しなくなる。
さらに、あるタイミングでテレアポし断られたとしても、数ヶ月後、改めて電話すると状況が変わっていてアポイントが取れることがある。そのため、継続的なテレアポ、電話営業も必要だ。
メール営業
テレアポ・電話営業はやりすぎるとしつこいなどといわれて電話できなくなる。さらに、最近では在宅勤務も増加し、担当者に繋がらないこともあるだろう。そこで活用されるのがメールだ。
個別にメールを送る、メルマガを配信するなど、メールを使ったセールスを行う。MA(マーケティングオートメーション)を導入すればメール配信を効率化・自動化できるため、インサイドセールスの業務効率化につながる。
メールであれば、テレアポ・電話営業よりも気軽であるため、継続性を出しやすい。
オンライン会議・商談
テレアポ・電話営業やメールなどである程度関係性が構築できたら、オンライン会議をつかって商談する。商談と言っても、リードの悩みや要望を聞き出し、解決策を一緒に検討するような個別相談のイメージが強い。こう言った相談を繰り返し行うことで、確度を判断しフィールドセールスにバトンタッチする。
以上が、インサイドセールスの主な営業手法のイメージだ。あくまで一般的な活動イメージであるため、御社の状況にあわせて、インサイドセールスの営業活動の内容を具体化してほしい。
資料一覧
インサイドセールスを導入・立ち上げる手順
では、インサイドセールスの導入・構築の手順を解説する。ただし、各社それぞれ事情が異なるため、自社の事情に合わせながら参考にしてほしい。
- インサイドセールスのリード受け入れ条件と送客条件を決める
- KGIとKPIを設定する
- インサイドセールスの活動を具体化する、営業シナリオを策定する
- 必要な人員をアサインしツールを選定する
インサイドセールスのリード受け入れ条件と送客条件を決める
インサイドセールスの導入・立ち上げ手順で、最初にやるべきことは、インサイドセールスがどこからどこまでをやるのか?の業務範囲の決定だ。インサイドセールスは何らかの方法で獲得したリードを受け取り、インサイドセールスの活動(テレアポやメールなど)を行い、何らかの条件を満たしたら営業部門(フィールドセールス)に送客しなければならない。そのため、「どんなリードを受け入れるか?」と「どんな条件になれば営業部門(フィールドセールス)に送客するのか?」を決めなければならないのだ。
これをインサイドセールスの「業務範囲」という。
「どんなリードを受け入れるか?」については、マーケティング部門など、リード獲得を担当しているメンバーと意見交換しなければならない。例えば「WEBからのコンバージョン(資料請求や問い合わせ)」「セミナー参加者」などはそのまま受け入れるが、「展示会で名刺交換したリード」は「受け入れない」といった具合だ。どんなリード獲得の施策を展開しているか?その確度はどの程度か?によって大きく異なるだろう。
受け入れない場合は、リード獲得の担当者(マーケティング部門など)がリードナーチャリング(見込み客の育成)を行い、受け入れ条件を満たすまでフォローを担当することになる。
「どんな条件になれば営業部門(フィールドセールス)に送客するのか?」については、営業部門と意見交換しなければならない。どういう条件だったらアポイントを取り営業フォローしてくれるのか?を意見交換し、条件を決める必要がある。ここで条件が厳しすぎるとなかなか営業部門(フィールドセールス)に送客できないし、ゆるすぎるとインサイドセールスの意味がなくなる。
インサイドセールスのKGIとKPIを設定する
インサイドセールスの業務範囲を確定したら、その業務範囲にあわせてKGIやKPIを設定する。KGIは営業部門(フィールドセールス)に送客できた数になるだろう。KPIは、「どんなリードを受け入れるか?」の条件と、「どんな条件になれば営業部門(フィールドセールス)に送客するのか?」の条件、そしてどんな手法でインサイドセールスするのか?の具体的な活動内容によって異なるだろう。KGI・KPIは業務範囲や具体的な活動内容が決まれば、自動的に決まることも多く、次の手順も絡めながら検討すると良い。
インサイドセールスの活動を具体化する、営業シナリオを策定する
インサイドセールスの業務範囲に合わせて、具体的な活動内容を検討する。まずはどんな手法でインサイドセールスするか?の手法選定や、どんなコンテンツ(ネタ)を提供するのか?のコンテンツ準備、さらには、どんなシナリオで営業するのかの営業シナリオの策定が必要となる。同時に、具体化した活動に合わせたKPI設定も行うと良いだろう。
必要な人員をアサインしツールを選定する
インサイドセールスの活動を具体化し、営業シナリオが策定できたら、必要な人員のアサイン、そしてツールの準備が必要となる。必要なツールとしては、マーケティングオートメーションツールやオンライン商談ツールなどである。
インサイドセールスは一般的にこのような手順で導入・立ち上げされる。そのため、まず重要なのは、インサイドセールスの業務範囲を決めることだ。リード獲得の担当者(マーケティング部門)や、フィールドセールス(営業部門)と意見交換し、どこからどこまでやるのか、しっかり意見交換し、社内合意をとっておく必要がある。
資料一覧
インサイドセールスに必須のマーケティングオートメーションツールとは
マーケティングオートメーション(MA)ツールとは、リードナーチャリング(見込み客の育成)と、リードクオリフィケーション(購買意識・確度の高いリードの選別・抽出)の業務を効率化することを主軸においたITシステム・ソフトウェアのことだ。インサイドセールスには必須ともいえるツールである。
マーケティングオートメーションは、主にメールを活用してリードとの関係性を継続的に構築することを支援してくれるツールだ。ターゲティングされたリードに対する一斉メール配信や、シナリオメール配信(ステップメール配信)、リードスコアリングといった機能を実装し、デジタルを活用した非対面営業に大きく貢献する。
マーケティングオートメーションの具体的な機能や仕組み、できることについては、下記のコラムで詳しく解説しているので参考にしてほしい。
インサイドセールスでマーケティングオートメーションツールを活用した効果
インサイドセールスにおいて、マーケティングオートメーションツールを活用した場合、さまざまな効果が期待できる。マーケティングオートメーションはメールを中心としたインサイドセールスが可能であるため主に下記のような3つの効果が期待できる。
- KGIやKPIの可視化(活動の効果の可視化)
- インサイドセールス業務の効率化(自動化)
- マーケティング部門や営業部門との情報共有
KGIやKPIの可視化(活動の効果の可視化)
マーケティングオートメーションはメールを中心としたインサイドセールスが可能であるため、メールマーケティングの効果(開封率やクリック率、CVRなど)を数値で可視化することができる。そのため、細かなKPIを可視化でき、インサイドセールスの業務改善につなげていくことができる。
インサイドセールス業務の効率化(自動化)
マーケティングオートメーションは、シナリオ機能(ステップメール)を実装している。シナリオ機能とは、ある条件を満たしたリードに対して、段階的に配信するメールのことだ。例えば、「製品Aの契約までの流れというWEBページを見たリード」に対して、WEBページを見た日を起点とし、3日後にメールAを、5日後にメールBを、という具合に、段階的にメールを自動的に送ることができる。さまざまな条件を設定し、さまざまなシナリオを設定しておけば、自動的にメールが配信されるため、インサイドセールスの業務を効率化することができる。
マーケティング部門や営業部門との情報共有
マーケティングオートメーションは、SFAといった他のシステムと連携するAPIを実装している。そのため、マーケティング担当者(マーケティング部門)やフィールドセールス(営業部門)との情報共有が可能となる。いちいちメールで連絡を取り合わなくても、ツール間で自動的に連携されるため、業務効率を高めることができる。さらに、フィールドセールス(営業部門)に送客した後の状況のフィードバックをもらうことで、インサイドセールスの活動を再開するといったことも可能となる。
ただし、システムが柔軟に連携できていることが条件であるため、システム連携ができていない場合は、手作業での連携となるため、この効果はあまり期待できない。
インサイドセールスを効率化できるその他のツール
マーケティングオートメーションツール以外にも、インサイドセールスで活用すると効果的なツールがある。
- 名刺管理ツール
- CRM
- SFA
- オンライン商談ツール
名刺管理ツール
名刺管理ツールは、これまでアナログで行っていた名刺管理をデータ化するツールだ。クラウドなどで名刺管理することができる。欲しい名刺の検索や、名刺に紐づく情報の管理が可能だ。
インサイドセールスにおいては、名刺管理ツールにより、営業接点を拡大することができる可能性がある。例えば、ある企業AのBさんに対して、何らかの営業メールや電話営業をするとき、企業AのCさんの名刺が名刺管理ツールにあれば、「Cさんとの関係」をBさんに連絡することで、Bさんとの信頼関係が強くなったり、話が膨らんだりする可能性があるのだ。
資料一覧
CRM
CRM(Customer Relationship Management:顧客関係管理)は、顧客に対して適切な対応をすることで、顧客と良好な関係を構築または維持していくことを言う。CRMツールは自社と既存顧客との関係を管理しているツールであるため、インサイドセールスの活動においても役立つケースがある。
たとえば、ある企業AのBさんに対して、何らかの営業メールや電話営業をするとき、その企業Aの親会社やグループ会社が既存顧客である場合、その実績や事例を個別に連絡することが可能だ。こういったことから、信頼関係が生まれ、営業送客のきっかけを作り出すことができる可能性がある。
SFA
SFA(Sales Force Automation:商談管理システム・営業支援システム)は、商談の状況や過去の履歴を一元管理して、組織的な営業活動を実現するツールである。現在自社で発生している商談の状況を一元管理できるため、フィールドセールス(営業部門)に送客したリードとの商談がどうなっているのか?などを確認することができる。もしフィールドセールス(営業部門)に送客後、アポイントが取れない、商談が進まないといった状況があるようであれば、送客の条件を見直すなどのきっかけにもなるだろう。
オンライン商談ツール
オンライン商談ツールは、Web上で商談をスムーズに行うためのツールだ。主にWEB会議システムが活用される。中には、オンライン商談に特化したツールもある。
インサイドセールスにおいては、メールや電話で説明するよりも、オンラインで対面説明する方がよりOneToOneの情報をリードに提供できる。リードの数が少なく、かつ売上単価も高いような商材の場合は、オンライン商談ツールを活用すると効果的なインサイドセールスが実現するだろう。
まとめ
以上、インサイドセールスの導入や立ち上げの手順、MAツールの活用などについて解説した。今後、インサイドセールスの重要性はますます向上するだろう。さらにデジタルセールスも重要となってきているので、ぜひ御社でもインサイドセールスやMAツールの活用を検討してほしい。
資料一覧