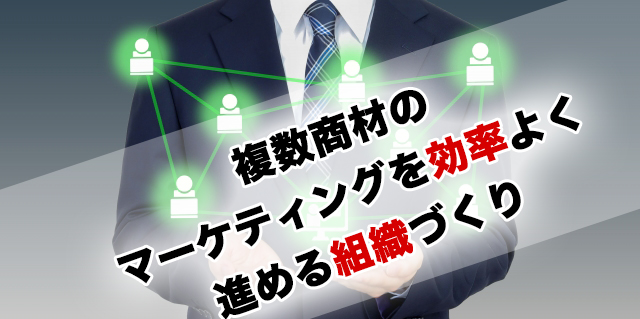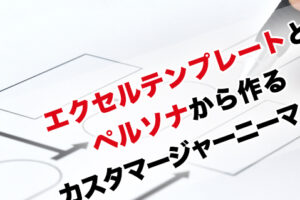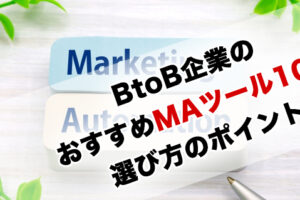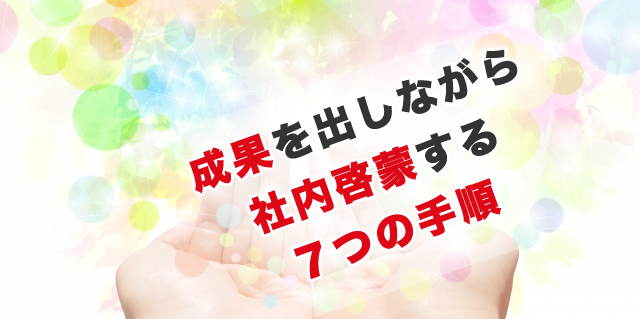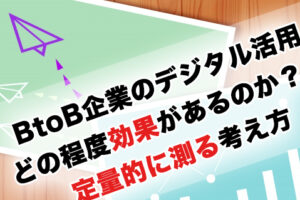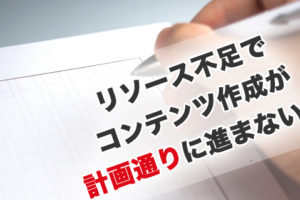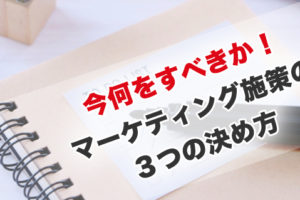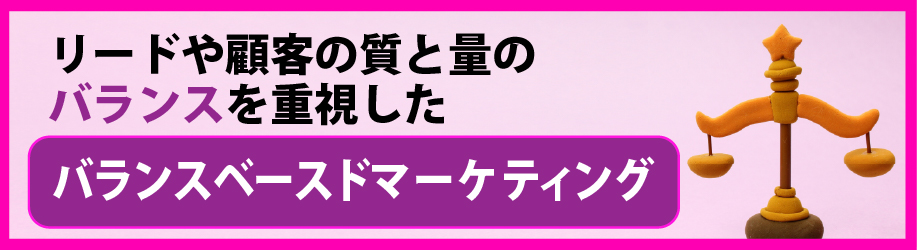複数の事業(もしくは複数の商材)を展開するBtoB企業で、デジタルマーケティングを推進する時、「どのように効率よくマーケティングを推進する組織を構築できるか?」が課題になる。実際に弊社にも以下のようなご相談がよせられている。

複数の事業や商材を扱う場合、その事業や商材の数に応じてデジタルマーケティングの施策工数が増大する。そのため、マーケティング部門は効率よく施策展開するスキルや業務の標準化といった生産性の向上が求められる。成果も出しつつ、生産性も上げていくという、非常に難しい挑戦が続くこととなる。
そこで今回のコラムでは、複数の事業を展開するBtoB企業向けに、デジタルマーケティングを効率よく進める組織づくりについて解説する。
デジタルマーケティングを効率よく進める組織づくり
最初に、複数事業やサービスがあるBtoB企業のデジタルマーケティング担当者は、日々、どんな状況なのかを少し整理してみよう。
- 複数事業・複数商材あるので、事業や商材ごとにマーケティング施策を展開
- デジタルマーケティング担当者は1人あたり数製品(事業)を担当、もしくは事業部ごとに担当者がアサイン
- デジタル施策(WEBやメール)だけでなくイベント(セミナーや展示会など)の支援も行う
- 事業部や営業部、開発部門からのWEB更新依頼やメール配信依頼にも対応
- 逆にこういうコンテンツを公開したらどうか?といった提案も行う
- 各事業・製品ごとでデジタルマーケティングに対する期待度や知識もバラバラ
- デジタル施策について、社内に標準化されたプロセスやスキルセットはない
- 各デジタルマーケティング担当者のスキルや知識はバラバラ
- デジタル施策に詳しい専門家が社内におらず相談できる人がいない(少ない)
- 人事異動で新規配属された担当者への教育体制も不充分
上記は、弊社が過去に関わった案件で感じたBtoB企業のマーケティング部のよくある状況である。複数事業やサービスがあるBtoB企業の場合、マーケティング施策も比例して多くなるため、どうしても上記のような状況になりがちである。
ではこういった状況を打開していくために、どのようにして組織づくりを進めていくべきか、そのポイントを2つ解説する。
ポイント1:KPIを少なくすること
効率良のいBtoBデジタルマーケティングを推進できる組織を作る最大の秘訣は、KPIの最小化(絞り込み)である。BtoBデジタルマーケティングのKGIは、リード獲得数やホットリード数などになることが多い。そのKGIに対してKPIをできるだけ絞り込もう。このKPIさえ改善(向上)できれば、KGIも連動して向上するといった形でKPIを最小限にすれば、やるべきことが最小化できる。やらなくていいことに時間を取られなくなる。
WEBやメールの施策を展開すると、離脱率、直帰率、PV数、滞在時間、開封率、クリック率などさまざまなデータがGA4やMAから取得できるが、そういった多くの数値をKPIにしてしまうと、その分比例して作業量も多くなる。そのため、このKPIを改善すればKGIが上がるという、重要度の高いKPIのみに絞り込むことがポイントだ。
これにより、以下の3つのメリットを得ることができる。
メリット1:知識負担を最小化できる
改善対象になるKPIは、多ければ多いほど、その改善に必要なノウハウやスキルをたくさん覚えなければならない。その結果、知識負担が増加し、覚えるまでに時間がかかることになる。そうなると覚えながら仕事するというような結果になってしまい、なかなか成長しないし成果もでない。
メリット2:作業負担を最小化できる
改善対象になるKPIは、多ければ多いほど、その改善にかかる作業数が増え、負担が増える。その結果、作業に負われることとなり、新しい技術やノウハウを覚える時間がなくなる。KPIは多ければ多いほど、いろんな視点で施策を確認できる反面、やるべきことが比例して増えてしまう。
メリット3:調整負担を最小化できる
調整負担とは、部門間(マーケティング部門、営業部門、開発部門、事業部門など)での施策調整をするときの負担のことだ。各施策の打ち合わせをする際には、どんな内容で何をして何を狙うのか?を関係者間で意見交換するが、そのとき、KPIが多ければ多いほど、あらゆる関係者からあらゆる意見がでてきて、収集がつかないといったことになる。そのため、事前にKPIを絞り込み、このKPIの改善・向上のみについて、意見交換を行うと調整しておけば、調整負担は最小限にできる。
もし絞り込んだKPIに関連のない意見を言われても、「余力のある時に検討しましょう」などのような形で、先送りすることもできる(KPIの改善以上に重要な指摘でない限り)。
ポイント2:KPIを改善する標準プロセスを作る
KPIを絞り込んだら、そのKPIを改善する標準プロセスを作ることが重要だ。これを教科書にして担当者が覚えることで、スキルの統一、新人への教育などが効率よく進められる。しかも、その標準プロセスは、過去の成功体験から作られたものであれば、非常に理想的だ。成功確率を高めることができる。
標準プロセスは、「KPI-Aを計測する方法と悪いときの改善プロセス」、「KPI-Bを計測する方法と悪化要因を見つけ出す方法」という具合に、絞り込んだKPIと連動したプロセスとし、いつでも確認できるよう、動画やPDF化しておくと便利である。
組織づくりと育成を支援する戦略フレームワーク
以上が、効率良のいBtoBデジタルマーケティングを推進できる組織を作る2つのポイントだ。弊社は最大のポイントはKPIの数だと考えている。なぜなら、上述した通り、KPIが多いと、それだけ担当者の作業量や知識負担が増大してしまうからだ。
しかし、絞り込みすぎるとKGI=KPIとなってしまい、意味がなくなるため、MECEなKPIを見つけ出せるかどうか?がポイントになる。
戦略フレームワーク「UFiC®」と「MaRPIC®」
弊社では、BtoBデジタルマーケティングに特化した戦略フレームワーク「UFiC®」と「MaRPIC®」を構築している。このコラムで記載したKPIの最小化と標準プロセスがセットになっている。
内容は、デジタルを活用したリードジェネレーションフレームワーク「UFiC®」とメール(MA)を活用したリードナーチャリングフレームワーク「MaRPIC®」の2つだ。
このフレームワークは以下のページで概要と事例をご紹介している。もしければ、一度ご覧いただけたらと思う。