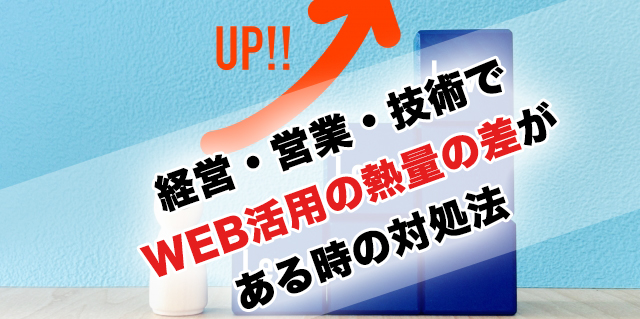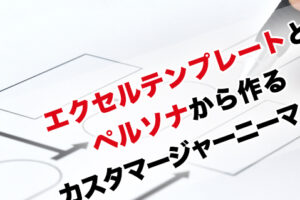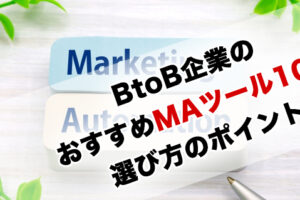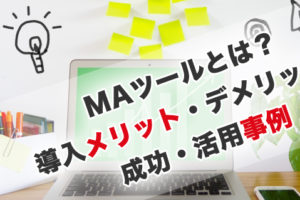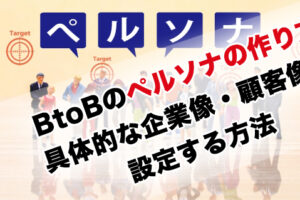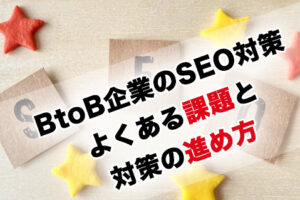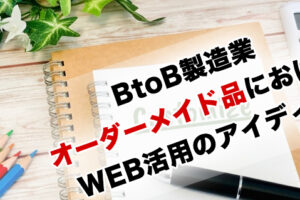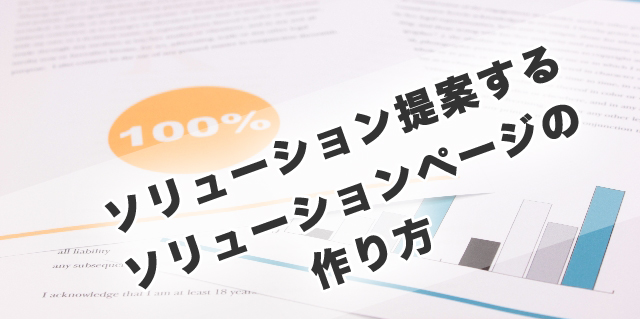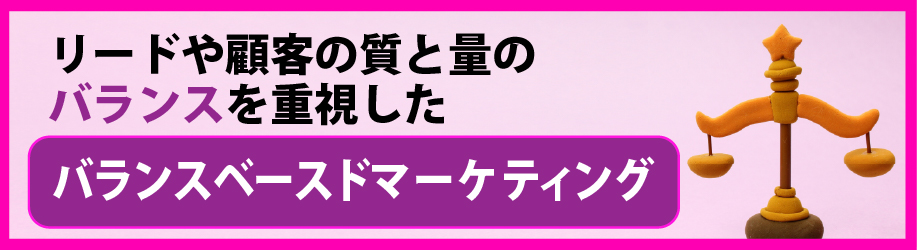BtoB企業におけるWEB活用の壁
BtoB企業において、WEBマーケティングによるリードジェネレーションの重要性は年々高まっている。しかし、実際に社内でWEB活用を推進しようとすると、思わぬ壁にぶつかることが多い。その代表例が、「WEB活用に関する熱量の差」だ、WEB活用を推進する部門(マーケティング部門など)と、営業部門や技術部門、さらには経営層との間で「温度差」があるのだ。
その熱量の差を示す代表例が、以下のような社内の意見だ。
- 「WEB活用しても売上につながるのか?」
- 「WEBはうちの商材には向いていないのでは?」
- 「情報を出しすぎると競合に見られてしまうからいまのままでいい」
- 「以前、WEBサイトリニューアルに大きなお金をかけたけど結果出てないよ?」
こうした意見に直面しながらも、自社サイトを営業貢献につなげていかなければならない。そこで、本コラムでは、「WEB活用の熱量の違い」という課題に焦点を当て、その背景と解決のコツをご紹介する。
BtoB企業でありがちなWEB活用の熱量の違い
経営層や営業部門、技術部門がWEB活用に消極的な主な理由をご紹介する。御社でも同じような理由でWEB活用の熱量の差が出ていることはないだろうか?
「WEBで売れるわけがない」という固定観念
BtoB企業の商材は高単価・長期検討型であることが多く、実際問題として、WEBサイトだけで営業を完結させることは難しい。そのため、「WEBで売れるわけがない」という考えは間違ってはいない。
しかし、「確度の高い見込み客の獲得を狙ったWEB施策」「毎月安定的な新規リード獲得を狙ったWEB施策」など、「リード獲得」という意味ではWEB活用は充分期待できる。つまり、WEBも使いようということだ。「WEBで売れるわけがない」という固定観念から抜け出せないと、WEBをどう使うか?という視点が抜け落ち、いつまでたってもWEB活用の熱量は変わらない。
営業の成果(売上)が見えにくい
営業部門は「売ること」が仕事であるため、「すぐに売れる」ことがないWEB活用は短期的な成果が見えにくい。営業部門や経営層からすると「WEB活用しても売上につながるのか?」と感じられやすい。
さらに、「以前WEBサイト作成に膨大なお金を使ったけどなんの結果も出ていない」などと言われるようなことも多く、なかなか熱量が上がらない。時代が変化し、BtoBでもWEB活用が盛んになっているということに気がつけていないということだ。
情報公開への抵抗感
製品情報やノウハウをWEBに出すことに対して、「競合に見られる」「お客様が営業を通さず判断してしまう」といった懸念を持つ営業担当者や技術担当者も存在する。「競合に見られる」については、確かにどこまで公開するか?の判断は必要になるが、「お客様が営業を通さず判断してしまう」については、考えようによってはプラスにもなる。
つまり、営業がわざわざ説明しなくてもよいというメリットがあるのだ。営業工数の削減につながる可能性もあるため、「どう考えるか?」次第であろう。これも固定観念の一種で、抜け出せない限り、WEB活用の熱量は上がらないだろう。
従来の営業モデルへの信頼
長年の対面営業や代理店経由の販売で成果を上げてきたBtoB企業ほど、WEB施策への投資に慎重になりやすい。いままでその営業手法で成果を出してきているため、わざわざWEBを活用する必要性を感じないのである。保守的な考えが根付いている企業ほど、その傾向は強いだろう。
デジタルリテラシーの差
経営層、営業部門、技術部門には、WEBマーケティングに対する理解が浅いケースや勝手な思い込みを持っているケースがある。
例えば、「うちの会社の製品を、仮に私が買うとしたら、WEBで検索なんかしない」や「WEB活用といえばデザインを変えるだけでしょ」といった具合だ。
つまり、デジタルリテラシーが低いため、「自分ならやらないという自分の意見に終始」したり、「何をやるのかわからない(わかっていない)」ため「勝手な思い込みで何をするのかの判断をしてしまう」といったことが発生する。これも固定観念であり、熱量が上がらない理由になっている。
以下のようなPDF資料が無料でダウンロードできます。御社の新規リード獲得のヒントになるかもしれないのでお気軽にお申し込みください。
リードがCVしたくなるホワイトペーパーの作り方を2つ(質重視のプロセスと量重視のプロセス)ご紹介!リード獲得の強化にお役立てください。
御社のWEBサイトで新規リードを獲得するための「WEB戦略のPDCAの回し方」をご紹介。WEBのKPIツリーのサンプルもあるのでPDCAをどう回すのかを具体的に学べます。
積水樹脂株式会社様、株式会社アシスト様、富士フイルムホールディングス株式会社様、株式会社日立ソリューションズ東日本様、山洋電気株式会社様、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様などの製造業・IT企業の成功事例です。どんな取り組みをしてどんな成果が得られたのか?がわかります。
BtoB企業向けに新規リードを獲得するWEBの作り方3つの手順を具体例を交えながら解説した資料。WEBコンテンツ作成の勘所・コツがつかめます。
熱量の違いを解消するコツ
ではこういった理由から抜け出していくにはどのようなコツがあるだろうか?そしてどのように熱量を上げていくべきだろうか?
BtoB企業向けにマーケティングコンサルを行っている弊社(株式会社ALUHA)の過去の経験から、コツを解説したいと思う。
WEB活用で何をするのか?の施策を共有
WEB活用といっても、人によって何をするのか?のイメージがことなるため、まずは、WEB活用で何をするのか?の施策を共有することから始めよう。BtoB企業の場合、デザインやキャッチコピーを変えるなどのような施策ではなく、「SEOや広告などでアクセス数を増やすこと」と「ホワイトペーパーなどをつかってコンバージョン(CV)を獲得すること」の2つの施策がメインになる。そのため、WEB活用でやることは、この2つだけであることを、社内の関係者に伝えて共有することが重要だ。
営業部門や経営層とのWEB活用のメリット共有
次に、営業部門や経営層に対して「WEB活用が営業活動にどう貢献するのか」を明確に伝えることである。特に以下の2点については重点的に伝えよう。
見込み客獲得コストの削減
従来の展示会やテレアポ、訪問営業、電話営業は、時間もコストもかかる。これに対し、WEB経由でのリード獲得は、初期投資こそ必要だが、長期的には1件あたりの獲得コストを大幅に下げることができる。WEBで公開している情報は削除しない限り、公開し続けるため、営業資産となり、費用対効果がどんどんよくなっていくのだ。
見込み客獲得の安定化
WEBサイトは24時間365日稼働する「営業担当者」である。展示会や広告のように一過性ではなく、継続的にリードを獲得できる仕組みを構築することができる。営業部門にとっても、「WEBがリードを供給してくれる存在」だと認識できれば、協力姿勢は大きく変わってくるだろう。
競合企業のWEBサイト分析で危機感を共有
競合企業のWEBサイトを分析し、その取り組みを可視化することも重要だ。
たとえば、競合が以下のような施策を行っていたとしよう。
- 製品別の導入事例を豊富に掲載
- 技術ブログで専門知識を発信
- ホワイトペーパーやeBookを活用したリード獲得
- SEO対策を徹底し、検索上位を独占
こうした事実を営業部門や経営層に共有することで、「このままでは取り残されるかもしれない」という危機感を喚起できる。特に、検索結果で競合に負けている現状を見せると、WEBの重要性を直感的に理解してもらいやすい。あるキーワードで検索し、競合は検索結果に出てくるが、自社は出てこないとなると、意識変化が発生し、熱量も上がる可能性がある。
成功体験の創出
そして、弊社が最も重要と考えるコツが、「成功体験」をつくることである。
いきなり全社的にWEB活用を推進するのではなく、スモールスタートでWEB活用を進め、成功体験を積み上げながら、熱量を高めていくのである。例えば、注力商材や新製品など、営業部門が関心を持ちやすいテーマを選定し、そのテーマに対してホワイトペーパーを作成する。そして、そのホワイトペーパーをWEBサイトで公開し、リード獲得できるかどうかを試すのだ。
仮に、いままで月数件だったコンバージョン(CV)が、ホワイトペーパーにより、2倍に増えたとしよう。そうすると、「ホワイトペーパーを作っただけでコンバージョン(CV)が増えた」という成功体験を作り出せる。当然、売上にはまだ遠いので、インパクトは小さいかもしれないが、こういった体験を積み上げていくことが重要だ。小さな成功事例を積み重ねることで、社内の「できるかもしれない」という空気を醸成することができる。
成功体験が生まれれば、社内の協力姿勢も自然と変わってくる。最初は懐疑的だったメンバーが、次第に「自分たちもやってみたい」と言い出すようになる可能性がある。
WEB活用の第一歩は「社内の温度差」に気づくこと
BtoB企業におけるWEBマーケティングの推進は、単なるツール導入やコンテンツ制作だけでは成り立たない。最も大きな壁は、「社内の温度差」である。
営業、技術、経営。それぞれの立場や価値観を理解し、丁寧に対話を重ねながら、少しずつWEB活用の意義を共有していくことが、成果への第一歩となる。そして、社内に小さな成功体験が生まれたとき、WEBマーケティングは単なる「施策」から「戦略」へと進化し、最終的には営業貢献、売上貢献という大きな成果を達成する可能性がある。
ぜひ御社でも挑戦してみてほしい。
以下のようなPDF資料が無料でダウンロードできます。御社の新規リード獲得のヒントになるかもしれないのでお気軽にお申し込みください。
リードがCVしたくなるホワイトペーパーの作り方を2つ(質重視のプロセスと量重視のプロセス)ご紹介!リード獲得の強化にお役立てください。
御社のWEBサイトで新規リードを獲得するための「WEB戦略のPDCAの回し方」をご紹介。WEBのKPIツリーのサンプルもあるのでPDCAをどう回すのかを具体的に学べます。
積水樹脂株式会社様、株式会社アシスト様、富士フイルムホールディングス株式会社様、株式会社日立ソリューションズ東日本様、山洋電気株式会社様、キヤノンマーケティングジャパン株式会社様などの製造業・IT企業の成功事例です。どんな取り組みをしてどんな成果が得られたのか?がわかります。
BtoB企業向けに新規リードを獲得するWEBの作り方3つの手順を具体例を交えながら解説した資料。WEBコンテンツ作成の勘所・コツがつかめます。